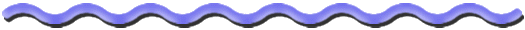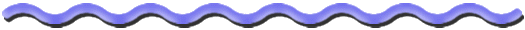関連作品情報
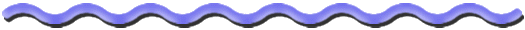
- 「使者」 {「無関係な死・時の崖」(新潮文庫)}の中の一編
-
「人間そっくり」の原型となった作品。こちらでは、いきなり「使者の詩」が出てくる。「秘めたる使命をおびてきた・・・」というやつ。設定は、脚本家ではなく、講演会場の控え室で出番を待つ講師奈良順平に自称火星人が現れる話になっている。結末は、「人間そっくり」のようなブラックなものと異なり、ドタバタ劇風に終わっている。
「人間そっくり」の発表は昭和42年、対して「使者」の発表は昭和33年だから、9年前には既に原型ができていたことになる。
- テレビドラマ版「人間そっくり」(安部公房全集09所収)
-
実は、「使者」の一年後に、その名もずばり「人間そっくり」というテレビドラマが放映されている。内容は、作品に行き詰まり、締め切りに追われている小説家、加島洋介の家に、頭のいかれた男とその妻がやってくるという設定で、小説版にかなり近い。しかし、小説家と彼の妻の間で他愛のない会話が交わされたりしていて、全体的に小説版ほどの悲壮感はない。書けない状態をそのまま、書こうとしていたりして、なかなか面白い。
テレビドラマだから、火星での生活シーンも入っており、どのように映像化されたのか知りたいところだ。そして、なにより気を引くのが、小説家に金子信雄、男に田中邦衛という、豪華な配役だったことである。^^)是非、ビデオ化して欲しいものだ。
- 「カーブの向こう」 {「カーブの向こう・ユープケッチャ」(新潮文庫)}の中の一編
-
「燃えつきた地図」の最後の部分で、探偵であった男がカーブの手前で記憶を失ってしまうという部分の原型となった作品。内容・筋ともほぼ同じで、その前に探偵が失踪人を探す話が挿入したものが、「燃えつきた地図」になっている。
違いとして、短編では男は女とともにカーブの向こうへ帰ってしまうが、「燃えつきた地図」では女の元に帰らず「失踪」してしまう点が挙げられる。
なお、この短編が発表されたのは、「燃えつきた地図」の発表の約二年前である。
- 「ユープケッチャ」 {「カーブの向こう・ユープケッチャ」(新潮文庫)}の中の一編
-
「方舟さくら丸」の原型になった作品。最後をみると、「志願囚人」プロローグとなっている。つまり、長編を念頭において、書かれた作品で、最終的には「方舟さくら丸」となっている。この点に関して、安部公房は、以下のように語っている。
最初はそういう題で考えていたんだ。「志願囚人」という発想をした理由は、いまわれわれが置かれている状況が、要するにそとから拘束された囚人ではなくても、みずから志願した囚人に過ぎないんじゃないかという問題提起をしたかった。でも、ずっと書き進めているうちに、それだけではまだ不十分であることに気づいたんだ。気がついて、「方舟さくら丸」という題に変えることにした。宗教的な言葉を一切使いたくないけど、これはある意味で人間の原罪を問う小説になるだろうな。方舟はむろんノアの方舟のもじりだよ。選ばれた者が生き延びて、その子孫を残すための、遺伝子プール作戦のための大シェルターさ。だから「方舟さくら丸」。ー(「錨なき方舟の時代」『死に急ぐ鯨たち』より)
このように、当初のプロットから大きく変更されており、本作品は、直接「方舟さくら丸」にはつながらないが、閉鎖系で生息できる「ユープケッチャ」という生物は「方舟さくら丸」に登場するし、「もぐら」を思わせる人物が主人公になっている。
- 「チチンデラ ヤパナ」 {「カーブの向こう・ユープケッチャ」(新潮文庫)}の中の一編
-
「砂の女」の原型となる短編。内容・筋ともほぼ同じで、砂丘まで昆虫採集に来た男(短編では、会社員の設定)が、「砂の家」に閉じこめられてしまう。閉じこめられたと気づいた男の行動が、「砂の女」とは異なっている。
- 「デンドロカカリヤ」 {「水中都市・デンドロカカリヤ」(新潮文庫)}の中の一編
-
初期(昭和24年)の作品でかなり難解。内容は、主人公であるコモン君が、植物へ変形してしまう話。この作品の中に、次のような一節が出てくる。
結局、植物への変形は、不幸を取除いてもらったばっかりに幸福をも奪われることであり、罪から解放されたかわりに、罰そのものの中に投込まれることなんだ。これは人間の法律じゃない。ゼウスの奴隷たちの法律だ。新しい、もっと激しいプロメテウスの火がほしい!
最初にこの作品を読んだときは気がつかなかったが、今読み返してみると、「鉛の卵」に出てくる緑色人を思わせる内容で興味深い。また、ゼウスが出てくるように、この一節の前にギリシャ神話に関するエピソードが出てくるが、ギリシャ神話にうとい私には理解しきれない。^^;)