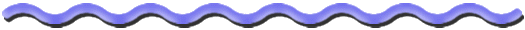
過去の資料を探すのはもうやめよう。
今ぼくに必要なのは、自分で書いた書評。
自分の意志で書いた、自分の書評でなければならないのだ。
感想文
ここでは、作品についての私の感想を公開しています。
なお、日付は私が感想を書いたときのものです。
このページはスタイルシートを使っていません。スタイルシートに対応しているブラウザはこちらへ
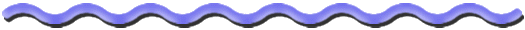
2000/03/11
非常にショッキングな作品だ。予言機械が映し出す過酷なまでの未来、その未来を前提として、海底開発協会のメンバーは行動する。「現在」では罰せられるべき犯罪を犯してまで。しかし、勝見がそれらを糾弾すると、彼らは未来の論理を使ってそれらの行為を正当化していき、次第に勝見の方が言葉を失っていく。自分の子供を、水棲人という「片輪の奴隷」にされたにもかかわらず。この作品は、私のよく見る悪夢を想起させる。内容は忘れるのだが、冷や汗がたらたら出てくる悪夢だ。目の前で起こっていることに対して、何か叫ぼうとしても、声が出ない、届かない。出来事を眺めるしかできない無力の状態になってしまう。勝見も頼木達の論理に完璧に打ちのめされて、言葉が出ない。妻の胎児を中絶させられ、自分自身もこれから殺されるというのに、叫ぼうにも、それが声となって空気を震えさせることができないのだ。 2000/02/13
安部作品というと、「砂の女」や「壁」などの不条理小説が有名だが、この「方舟さくら丸」は、エゴとエゴがぶつかり合い、調和することなく発散していく過程を描いた作品で、「飢餓同盟」に通じる所がある。もぐらのエゴ、昆虫屋のエゴ、もぐらの生物学上の父親である猪突のエゴ、猪突に率いられた老人集団ほうき隊のエゴ、ほうき隊に対抗する若者集団ルート猪鍋のエゴ、それらのエゴが互いに食い合う奇態、それは、まるで多くの業者のなわばり争いによって奇怪な迷宮になった地下採石場跡のように。
1999/10/16
段ボールを頭からすっぽりかぶった箱男。子供の遊びならともかく、大の大人がすることじゃない。そういうことをするのは頭のいかれた奴だ。しかし、そこには何かしら甘い誘惑を感じさせる存在でもあるのだろう。その存在を抹殺しようとすればするほど、その存在に惹かれていく。そんな不思議なパラドックスを持っている。一体、そこにどういう魅力があるのだろうか?
1999/9/25
文庫本の背表紙の紹介文を読むと、『会社を首にされ、生きたまま自分の「死体」を売ってロボットにされてしまった機械技師が、人間を酷使する機械を発明して人間に復讐する』作品となっている。簡潔に要約された文章だが、最後の「復讐」という言葉が当てはまるのかどうか、違和感を感じた。
1999/9/12
安部文学の永遠のテーマとして「他者への通路」というものがある。これは、本質的に孤独な人間が、他人とどのように向き合うべきかを問うものである。この初期の作品においても、そのテーマがしっかり見受けられる。
1999/8/21
私は、安部作品が好きだ。その魅力は、価値観の逆転(パラドックス)につきると思う。我々が安住する常識への挑戦そして破壊、非常識と捨てている物にこそ価値が有ると主張し、そしてその非常識が成長し、やがてぱくっと常識を呑み込んでいく、その過程が実に鮮やかだ。
1998/11/23
バイト先の休み時間に読んだのだが、読み終えた後、「また、すごい作品に出会ったな」と思った。この作品のほとんどは、「こんにちは火星人」という火星人を題材にした、打ち切り間近のラジオ番組の脚本を書く構成作家と彼の家を訪問にきた自称火星人との会話で構成されている。SF映画に出てくるたこ足の火星人のように我々とは異形の者なら、我々は無条件でそいつが火星人であることを認め、すぐさま友好または敵対行動をとるだろう。しかし、この男は地球人そっくりで、そこがこの作品のみそになっている。我々とうり二つなわけで、それ故地球人と見なすのが自然で、それ以外の可能性はまず考えない。それでもなお、火星人と言い張るなら、そいつは気違いに違いない。実際、脚本家も気違いと思うが、その男は言葉巧みに脚本家の、そして我々の常識を壊していく。
「公理」ー数学用語、論理を進める上での前提条件となるものであり、そこから定理等が導かれる。しかし、その性質上証明はできないものである。一例として、ユークリッド幾何学では、公理の一つとして「同一平面上で、直線外の一点を通って、この直線に平行な直線は、ただ一つだけ引ける」というのものがある。
1997/2/21
大分前に読んだ安部公房の「鉛の卵」は、含みのある作品で面白かった。遥か遠い未来にタイムトラベルした科学者が、目の当たりにした世界は自分で光合成できる人種「緑色人」の社会だった。そこでは食物を口にすることが一切禁じられており、その禁を破ったために彼は追放される。そして、外の世界が実は科学の発達した鋼鉄の都市であると分かり安心するが、なぜか緑色人の禁欲的な社会に後ろ髪を引かれる思いもしたという話だ。
1994/11/8
平凡な教師が、昆虫採集に出かけた砂丘で村人たちに、周りを砂で覆われた「砂の家」に監禁されてしまう。男は、何も村人たちに損害を与えないようとしていないのにもかかわらず、砂堀りをさせられるという全く理不尽な話だ。復讐でも何でもないのだ。ただ、この村に来てしまったというだけでだ。男は理不尽に腹を立てて脱出を試みては失敗する。しかし、この話は単なる脱出劇ではない。面白いことに、理不尽の最たる者である「砂の女」と共に生活していく内に、男の考え方が一変してしまうのだ。最初は頑強に村人たちに抵抗するが、それが駄目とわかると、欺くためとはいえ、砂堀りに参加し、最終的にはその行為に充足を感じる。多くの収入を得られる教師の仕事よりも。仕事や家庭のある今までの生活に戻ろうと躍起になっていた男は、脱出の失敗を繰り返す内に、取り戻そうとしていた、失ってはいけないはずのものがいったいどれだけのものであるかという疑念を抱き始め、「砂の家」での生活の方がもっと満ち足りているのではないかという気持ちに変わっていく。妻よりも、「砂の女」の方がよほど魅力があり、いとおしい。入れ替わっていく生徒を眺めて、自分だけ老いていく教師よりも、目的のはっきりした砂堀りの仕事の方が、よほど心が満ち足りる。逃げるべき「砂の家」と、戻るべき「今までの生活」が、あべこべになる。そういったパラドックスが、現代を象徴しているのではないだろうか?他人の前で女と性交すれば外に出られるという理不尽な条件を、理不尽と思わず、女に嫌がられてまでしようとする。そして、加害者である村人たちが、実は都会に対して怒りを持ち、男は自分が都会人であるために、加害者の一人ではないだろうかと思ってしまう。そういう2面性・パラドックスがこの小説の主題だと思う。
私は、未来にどうしても耐えられない。そこで、まず勝見と同じく、「予言機械」の正当性を考えてしまう。誤差のない予測(シミュレーション)なんて、ナンセンスだし、予言を知った場合の行動をn次予言値としてカバーしているかのように見えるが、2次予言にしたって、誰が・いつ・どこで・どのような状況で、1次予言を知ったかによって変わるべきで、それを刻々と計算していると、時間が足りないはずだ。しかも、作品中に出てくる二次予言値も相当妙な存在である。単なる予言で人格などない、と言いつつ、勝見を殺す段になって「私だってつらい」と感情を滲ませるのだ。また、勝見がいくら予言を鵜呑みにしては危険だと叫んでも、海底開発協会のメンバーは取り合おうとしない。その正しさは絶対的で、それからの論理だと、勝見は未来に対応できない人間として裁かれる運命にあるらしい。しかし、そのような未来を受け入れられないのは私も同じで、だからこそ「予言」の正当性を疑わざるを得ない。予言機械が語る未来の過酷さを思うと、なおさらに。
しかし、「予言」を「預言」と読み替えると分かるような気がする。ちょうど、ノアが神から洪水の預言を聞いたように。勝見もまた、自ら作った予言機械から預言を授かったのだ。しかし、傲慢で残酷なノア(少なくとも安部にとっては)と違い、断絶に耐えられない勝見はその預言を信じることができなかった。故に、未来の論理によって裁かれ、代わりに弟子達・海底開発協会がノアにならざるを得なかったのだろう。海の主人となるべき水棲人類の父親となる、ノアに。勝見が責めを受けるとすれば、未来予測という神の領域に足を踏み入れたにもかかわらず、神の言葉を信じられなかったという一点に尽きる。しかしながら、そのことこそが、予言がタブーであることを暗示していると思う。
さらに、物語の後半で、予言機械によって未来が映し出されていく。ただし、それが「実際」に起こることなのかどうかは、一切語られることはない。ただ映されるのみだが、その未来像はとてもリアルに迫ってくる。洪水、水棲人社会の到来、水棲人社会の日常、「風の音楽」にあこがれる水棲人、などの物語。それらに対して、私たちはもはや判断することはできない。ただ眺めるしかないのだ。でも、本当にこの「ブループリント」は正しいのだろうか?
いや、もう予言だの水棲人社会だの言うのはよそう。たとえ、近い将来、水棲人を眺める望遠鏡のように水没していく運命にあっても、我々は「現在」を生きるしかないのだから。
核シェルターで生き残ろうとするのは、強烈なエゴの現れだ。全世界の人間が焼け死んでも、自分だけは生き残っていたいという、人間の持つ最大級のエゴだ。このような考えは、自己中心的と非難されるべきものであるが、果たしてエゴのない人間などこの世にいるだろうか?何が言いたいかというと、他人よりも自分が大事なのだというエゴは、誰もが持つ人間の本質的な要素であり、そして同時に問われるべき原罪でもあると思うのだ。
もぐら自身も「実際に生き延びることよりも、最後の瞬間に、生への希望を持ちつづけることのほうがずっと大事だろう。」と語っている。核戦争が起きて人類の大半が死滅したときに、自分が他人よりもすこしでも長く生きていることを確認すること、それ自体が方舟の目的だったのだ。生き延びた先の目的・計画など、彼には何も無かった。むしろ、ほうき隊副官の方がその計画には長けていただろう。遺伝子プールのための、女子中学生狩りとかね。結局のところ、彼には生き残った後の生活など念頭になく、彼が欲していたのは閉鎖空間ならびに、その中での長という地位だった。しかし、便器に足を吸い込まれて身動きがとれなくなってしまうことにより、その望んでいた地位も失い、彼は傍観者になってしまう。なんと、みじめな道化役だろう。さらに、残った者たちの武器である便器を塞いでいることによって、彼の立場は一層危うくなるが、この窮地を救うのは意外にもサクラたちだった。もぐらは女性のサクラに好意を抱いていたから、できれば一緒に脱出して欲しかった。しかし、それも失恋に終わる。
「街ぜんたいが生き生きと死んでいた」、これは物語の終わり近くの描写である。街はいつも通りの風景だったのだが、誰一人として仲間を連れてこられずに街に戻ってきた彼には、「死」とは無関係にいつも通りに活動している街を、自己喪失の状態でただ呆然と眺めるほか無かったのだろう。
もぐらが持っていた、ユープケッチャ的思想、つまり閉鎖空間で生きること、「個」単体で生きようとすること、それは皆が心の底で持つ願望・夢想だろうと思う。しかし、子孫を残すこと、食料、その他もろもろの問題から、仲間が必要だ。普通の人は、家族・企業・国家に属すことによって、仲間を獲得する。一方、もぐらは「生きのびるための切符」を発行して、それを理解してくれる仲間を求めた。やはり、方舟には社会・他者との干渉・交渉が必要で、つまりは新しい共同体を一から造ることにほかならない。ただし、船長は俺だ、ともぐらは精一杯に主張する。しかし、彼には長としての力量は無かった。そういう共同体は、イス取りゲーム、つまり生存競争の世界だ。エゴとエゴの間に、もはや調停はあり得ない。強いエゴが弱いエゴを倒して、力のピラミッドを築く。その先に待っているは、軍隊のような組織化だけだ。結局、昔の共同体への回帰になってしまっている。
都市への方向、「個」の方向に進むべきだというのが、安部の主張で、実際我々はその方向で経済発展してきた。しかしながら、古い共同体の亡霊はなおも生き続け、エゴを持て余した人間を見つけては、そこへ回帰させようと巧みに誘惑し続ける。個と共同体との闘い、それは永遠の闘いかも知れない。そして、その間を涼しい顔で巧みに綱渡りするサクラは一種の救いだ。決して、根本的な解決ではないが。
名前を消すこと・存在を消すこと、それは社会生活の喪失を意味するはずだが、同時に社会生活からの解放を人々は、心のどこかで望んでいるのだろう。そこに箱男への誘惑がある。だから、冒頭のAは、箱男を空気銃で撃つことで、自分の箱男願望に気づき、贋箱男も、箱男の箱を欲しがる。
贋箱男、これはまた面白い存在だ。箱男自体に胡散臭さを感じるのに、さらに輪をかけて胡散臭い。でも、不思議なことに、安部作品だと、なにかしら実感を持たせる。私は、既に安部マジックにかかっているようだ。さて、物語の後半になってくると、箱男が主人公の座を奪われ、誰が主人公か分からなくなる。ここが、この作品の白眉だ。しかし、それはたいしたことではないのだ。箱男とは、自ら存在証明を消した人間。だから、誰が箱男であるか証明することはできないし、逆の言い方をすれば、作品中に出てきた人間は、すべて箱男の資格があるということだ。当初箱男と思われていた「ぼく」でも、AやAに撃たれた箱男でも、贋箱男でも、軍医殿でも、贋医者でも、ショパンでも、少年Dでも、「覗き見る」或いは「覗き見られる」という共通項だけで、箱男足りうる。
そして、誰が箱男であるか分からないということは、箱男に関する一切の出来事・記述は、その真実性を確かめることができないわけで、もはや真実と虚偽の境界は意味をなさない。
では、この作品を語ることは、そもそも不可能なことなのだろうか?少なくとも、推理小説のように、何が真実であったかを追求することは不可能である。ここは、秩序が崩壊した世界だから。旧来の小説と異なり、複数の主人公とストーリーが存在して、さらに互いに矛盾している。ストーリーを小分けして語ることはできるが、果たしてそれで充分と言えるだろうか?どうやら、私には、これ以上箱男の迷宮を探索することができないらしい。迷宮をさまよい続けるほかないようだ。
これは、少々難しい問題だから、その問題に取りかかる前に流れを整理しておこう。まず、機械技師がロボットになったのは、関係の逆転として捉えることができる。つまり、本来機械技師は機械をつくる立場だが、機械技師自身が機械に作り替えられてしまう、このような立場の逆転は、安部作品では珍しいことではない。機械にされてしまった哀れな機械技師は、「R62号」と呼ばれるが、彼はやがて生産性を高めるためには、機械を人間に合わせるのではなく、人間を機械に合わせるべきと考え、人間を酷使する機械を発明する。これもまた、人間と機械の立場の逆転である。そして、その人間を酷使する機械は、自分を首にした社長を殺してしまう。R62号を「人間」と見なせば、これは復讐と言えるだろうが、R62号は、人間的な感情のない「ロボット」であるから、復讐などは考えていないだろう。むしろ、生産性向上という純粋な目的達成のために機械を製作したと考える方が自然だ。そして、それが結果的に殺人を引き起こすという皮肉な内容になっている。
この作品に、機械文明に対する警告・警鐘というような教訓を見いだしても無意味に近いと思う。アンチ技術というのは、安部自身が否定しているし(技術とは、プログラム全体を意識すること)、問題は、暴走してしまう人間だと思うからだ(狂気的なプログラムが問題)。では、機械文明を肯定しているかというと、そうでもないらしい。この作品のような、悪夢的世界になるかも知れないのだから。単純な賛成または反対でなくて、むしろ技術をコントロールしていくことが重要だろう。
最後に反論を一つ挙げておく。生産性向上のためには人間を酷使すべきというくだりがあり、その理由は人間の方が機械よりもコストが安いと言っているが、果たしてどうだろう。昨今の企業経営を見ると、過剰な人員コストに苦しんでいるように見えて仕方がない。例えば、人間1人で、1年間300万かかることを思えば、10人の首を切って、3000万の機械を買った方が、その先のことを考えれば、得なはずである。つまり、機械の方が人間よりも安いのだ。既に単純な作業の多くが、機械に置き換えられている。この現状を見ると、人間を酷使するよりも、機械に置き換えていくべきなのだろう。で、余った人間は何をすればいいかというと、機械にできないような創造的な仕事をしていくしかあるまい。
この作品は、主人公の部屋に、見知らぬ一家がやってきて占領してしまう話だ。他の作品にも見られるように、主人公と他者との間に大きな壁があり、距離感がつかめない。つかめないままでいると、このような不意打ちを食らって、痛い目に遭う。他者から自己への侵入、それが鮮烈に描かれている。「砂の女」の場合と同じように、この状況になってしまっては、彼にはもはや逃れる術はなく、奴隷のごとき生活を余儀なくされる。
いきなり、悪魔(=死刑執行人)はやってくる。最初から、逃れられないということがハッキリしている点では、神話的構成といえるかも知れない。つまり、罪無き罰を受ける主人公は、最初から崖っぷちにいるわけだ。そして、何とか抜け出そうと、他者と、そして外界と格闘する、その果てになにがあるだろうか?いや、結末は重要じゃない、意味があるとすれば、むしろその過程だろう。それが、つまりは人生そのものなのだから。
さて本作は、探偵である主人公が、根室洋という失踪人を探す過程で自分を見失うという話だ。まず、気になったのは、最後の部分。探偵が、依頼人である失踪人の妻の部屋で休んでいる間に、舞台がふっとんでしまう。カーブの手前―この風景は、作品の冒頭に出てきた、失踪人の妻の団地につながるものと同じものーで、男は、自分が誰であったかを忘れている。実は、この部分には、原型となる短編「カーブの向こう」という作品があり、ほぼ似たような話になっている。この部分がメインで、探偵の失踪人探しは付けたりのようなものであり、両者に直接的な関係はほとんどない。男が探偵であり、ウェイトレスの女が失踪人の妻であり、カーブの向こうが彼女の住む団地につながると読みとれるが、真相はわからない。
さて話を戻すと、男は、カーブの手前で立ちつくす。ここはどこか、そして今はいつだろう?恐らく、勤め先からの帰宅途中。しかし、自信はない。立ち寄った喫茶店で、手探りしながら、自分が誰であるかを考えてみる、でもわからない。そして、公衆電話で、知り合いと思われる女性に電話をかけて、物陰に隠れて誰が来るか様子を窺う。来たのは、喫茶店のウェイトレス、彼は、そうだったかもしれないと思う、しかし、彼女の前に出ることはせず、反対の道を歩き出す。
結局、事件の発端である、失踪人根室洋と同じように、この男―そして、おそらく探偵であった男―は「失踪」してしまう。ところで、依頼人の弟との会話で、失踪の原因は記憶喪失か気が触れてしまったのかのいずれかが考えられるという話が出る。では、彼は、果たしてどちらのケースに当たるのだろうか?気が触れたわけではないので、記憶喪失のケースのように思われるが、単に記憶をなくしたというより、自己を喪失したように思われるのだ。実際、彼は「自分を落とした」或いは、「自分に落とされたのではなかろうか?」とつぶやく。名前・会社・自分の町、帰属していたはずのすべてものが失われた彼は、その失ったものを、探そうとするが、その途中であきらめる。「探し出されたところで、何も解決しない。」他人によって、記憶の空白を埋めてもらうだけの話。だから、彼は彼女とは別の道を歩み出す。むしろ、この最後の部分で、物語は始まるのかも知れない。
ところで、記憶を失った当初と最後の彼は、大きく異なっている。自分が誰であったか、どこに行くべきか、迷宮の中で迷子となった彼と、捜索者から姿を隠し、自ら探索者として迷宮を進む彼では、別人のようだ。その違いの原因は、…。名刺の電話番号に電話して、女が来るのを待つのが転換点だろう。必死に、過去への通路を探ろうとして電話したはずだ。しかし、その直後に、自分の下に、新聞紙に包まれた大便があるのに気づく。大都会の中で、公衆電話の中で大便を余儀なくされた男の姿を想像して、ぞっとする。それは、閉所に閉じこめられたものの象徴だ。そして、彼は「誰だって、狭い既知の世界に閉じこめられていることに変わりはないのだ。」と言って、自分の状況を一般化している。そして、周囲の人々に注意を向け出す。そのときの彼は、もはや迷子ではなく、探索者になっている。捜索者が、迷子になる可能性も考える。「やってくる救いの主が、自分の地図を省略だらけの略図に過ぎないと自覚させる、地図の外からの使いだとしたら…その使いもまた、存在しながら存在しないあのカーブの向こうをのぞき込んでしまったとことになるのだ。」自分の地図は、自分で探すしかない。与えられた地図は要らない。短編では、彼は捜索者に救出される迷子でしかないのに比べると、大違いだ。
しかし、最後の彼の行く末を考えると、もはや私の想像の域をこえてしまう。彼が、どこに向かっていくのか、なぜこれほど気楽な気持ちでいられるのか、全くもってわからない。彼もまた、「理解できない地図をたよりに歩き出す」としか言わない。自分でもわからないはずだ。しかし、ここで作者である安部公房は、何らかのメッセージを投げかけようとしている、そのように思われた。安部公房の言葉として、「人間の脱出とは何か、いったいどこに抜け出して行けるのか、僕には答えられないし、答えられる人がいるとしたら、たぶん詐欺師だろう。抜けた先の世界を言葉にできるのは宗教だけさ」(「都市への回路」より)というものがある。この作品の主人公が、果たして脱出できたのかどうか、それはわからない。しかしながら、そこに何らかの脱出の糸口があるのかも知れない。
脚本家の厳しい追及にもかかわらず、彼が火星人でなく地球人であることを証明できないのだ。我々が常識とするところの-我々は地球に住む地球人であること-当たり前過ぎて言うのもはばかられるくらいの常識が実は「公理」に過ぎないのではないかと疑わせる。火星に偶然に生物が存在し、偶然に地球人並の高等生物で、偶然にも地球人とうり二つかもしれない。偶然を仮定すれば、その可能性は否定しきれない。自称火星人の言うところのトポロジー的論理だ。
話を進めていく内に、脚本家は知らず知らず自称火星人のペースにはまっていき、ラストのブラックな結末へと辿り着く。彼は、自分のおかれた状況をわかりかねるまま途方に暮れてしまうのだ。自分がどこにいるのかわからない、相手が何者かわからない、迷子の感覚のままで終わっている。最後に彼は読者に、何が真実なのか問いかける。「ここは、寓話が実話に負けた世界なのか、それとも実話が寓話に負けた世界なのか。」
脚本家の考える実話の世界、自分が地球人で、自称火星人は地球人の気違い(自称火星人の言葉を借りれば、「火星病」にかかった地球人)という認識。それに対して自称火星人の言うような、自称火星人は本当に火星人で、自分は「地球病」にかかった火星人という寓話。そのどちらが勝ったのだろう?自分の考えていた実話が寓話で、自称火星人の寓話が実話なのかもしれない。いや、それでもいいのかもしれない。脚本家を真に不安にさせるのものは、「そのどちらか判別つかないこと」、「結論がでないという結論」、「実話と寓話が入り交じって分離できない」という不確定性なのだ。
この話の主題は、緑色人が食物を消化する胃自体を消化したように、欲望自体を消滅させるか、それともあさましく食物を奪い合ってまで欲望を充足し続けるか、という二者択一であると思う。禁欲的な社会の中で幸せを見つけるか、それとも現代社会のように技術を尽くして欲望を拡大し続けるか。そして、おそらく禁欲的な社会というものに人間はなじめないことまで暗示している。なぜなら、一見理想に見える緑色人社会には、快楽がないからだ。張りがないのだ。金を貯める楽しみもなければうまいものを食べる喜びもない。死の苦しみを無くすことで、生の喜びを失ってしまっているのだ。逆説的に言うと、欲望こそ人間の生きる原動力なのだ。欲望なくして人間は人間として生きていけない。だから、人間は欲望を満たし続けていかなければならない。たとえ底なしであっても。