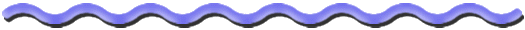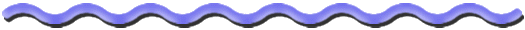「何処でどう生きようと、たいして代わり映えしないよ。
それに本来、嘘を承知ではしゃいで見せるのがさくらだろ。」
(方舟さくら丸より)
安部公房を語る
ここでは、作家「安部公房」にスポットライトを当てて、その世界観を探ろうとしています。
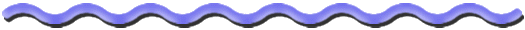
- 人間の値段
-
人間を物質的・即物的に見たとき、必然的にそれには値段がついてくる。値段のついていない「もの」の方が、希だろう。
『R62号の発明』では、主人公の機械技師は、その命を売り、『第四間氷期』では、主人公の妻の胎児を、無理矢理買い取られる。逆に、『耳の値段』『手段』は、「保険」という、現実社会で唯一認められている人間の格付けを利用して、儲けようとする話だ。
人間に値段をつけることはタブーだが、あえてそこに挑戦するところに、既成概念の徹底的破壊を目指した、安部らしさが見られると思う。
- 国境という名の境界線
-
ある概念と対立概念の間を行ったり来たりする、安部独特の作風は、「境界線上の思考」と言い表される。これは、旧満州で幼年期・青年期を過ごした安部が、国境という地球上で一番大きな境界線がダイナミックに変動する様を目の当たりにしたことが契機になっていることは、間違いないだろう。
- カメラ
-
安部公房は、カメラ好きである。単なる趣味を越えて、『箱男』には、自ら撮った八枚の写真を載せており、『笑う月』の「シャボン玉の皮」では、その写真が好評だったことと、それが意図するところが「ゴミ」であり、自分は何故か「ゴミ」に惹かれてしまうのだと述べている。
また、『箱男』や『方舟さくら丸』では、主人公は元カメラマンという設定になっている。不思議なことに、それらの作品でカメラを撮るシーンはほとんど無い。となると、カメラマンという設定は、人物の無名性と同じように、無くても良さそうな気がするのだが、少なくとも『箱男』の場合は、「覗く男」として意味ある設定なのだろう。
- 無機物と有機物
-
これは、「壁」の中の一節だ。「壁」では、主人公のS・カルマ氏は、名前を失い、題名通り壁になってしまう。一見荒唐無稽な展開のようだが、このような変形は、安部作品では決して珍しいことではない。安部公房は、生物・有機物と鉱物・無機物を対比し、等価的に見ているから、その関係を逆転させてみただけのことなのだろう。
- 探偵
-
「燃えつきた地図」における主人公の職業は探偵である。失踪人捜索の依頼を受けて、すべての情報に疑いを持って、捜索を開始する。彼は、依頼人の弟についてさえ疑いをもつ。しかし、その線も依頼人の弟の死によって、訳が分からなくなる。
彼ばかりでなく、安部作品の主人公というのは、疑い深い人間が多い。その点では、彼らは「探偵」と言える。探偵というと聞こえはいいが、常に他人を疑わずにいられない孤独な人間だ。自分一人では、何ら信じるに足る物を持ち得ず、都市という迷宮を探索し続ける。そんな人間が異世界に足を踏み入れたら、彼は本当にひとりぼっちで隔離・孤立されてしまう。例えば、「砂の女」では、砂堀りという、農村の奇妙な習慣を強要され、「人間そっくり」では、気違いの妄言に、正気を失ってしまう。異世界に迷い込んだ探偵は、もはや元の世界に帰ることは許されず、悪夢のような世界に閉じこめられてしまうのだった。
- 無名性・匿名性
-
彼の作品の登場人物には、ちゃんとした名前を持っている人が少ない。そもそも名前が語られなかったり、アルファベット一文字で済まされたり、最後に付け足しのように書かれていたりする。また、その人を特徴づける描写も少なくて、その人物のイメージを捉えづらい。しかし、これは矛盾するようなことだが、非常に自分に近い存在のような気もするのだ。これは、登場人物の情報の少なさが、逆に主人公に自分の像を投影しやすいしくみになっているかも知れない。実際、個性的な人物が登場する「飢餓同盟」や「方舟さくら丸」では、自分に近いと思える人は見あたらない。
なお、無名性に関して、安部自身も
もともとぼくの作品の登場人物に、名前がつけられていること自体、極めて例外的である。たいていの場合、代名詞だけで済ませてしまっている。たまに名前を名乗って登場してくる人物があっても、深い意味はなく、やむをえずつけた符牒ていどのものに過ぎない。出来れば名無しのままで済ませたいと思う。それで不都合を感じたことはめったにない。たとえば、『砂の女』の仁木順平にしても、失踪後、手続上の必要からはじめて明かされた氏名であって、主人公として活躍中は、単なる男にしか過ぎなかったからだ。登場人物の無名性は、ぼくの作品にとって、どうやら不可欠の条件らしいのである。
と語っている。(「藤野君のこと」『笑う月』より)
- 未発表詩見つかる
-
今まで、最も古い彼の作品は、昭和22年(彼が23歳の時)に自費出版した、ガリ版刷りの「無名詩集」ということになっていたが、新たに10代の時に書いた詩が都内の友人宅や遺族の遺品の中から見つかった。これらの詩には、「砂」「荒野」など、彼の代表作「砂の女」などに繰り返し描いたモチーフが既に出揃っており、彼の揺らん期を知る貴重な作品で、安部公房全集第一巻に収録される。
(1997/1/10 読売新聞より)
- 二重性・関係の逆転
-
安部公房は、物の表と裏が同時に見えてしまう人なのだと思う。「砂の女」では、男は、逃げることから住むことに変わり、「燃えつきた地図」・「誘惑者」では、追う者が追われる者になり、「人間そっくり」では、どちらが正常で、どちらが異常か、わからなくなり、「箱男」では、見る者が見られる者へ変わっていく。これが、単なる概念の遊びなのか、そうでないのかは、読んだ者で判断してほしい。
- 偽物
-
本物と偽物、二重性を見抜く目を持つ安部公房には、両者に対等の位置づけをして、さらには偽物が本物になり、本物が偽物になっていく。その代表的な作品は、「箱男」・「人間そっくり」が挙げられるだろう。
- 境界のあいまいさ
-
追う者と追われる者、見る者と見られる者、現実と妄想、そこに境界線を引こうとすればするほど、その境界線はぼやけていく。彼の作品を読むと、そんなことを考えてしまう。
- 様々な表現方法
-
彼の表現手法は、文字のみならず、写真(彼の趣味でもある)、公文書・手紙・広告・名刺(文書の四つ角を見せることで、文字とは異なる趣を出している)など、様々な表現方法を模索していた。さらに、舞台上演など、小説家の枠にとらわれない活動をしていた。
- 落伍者のイメージ
-
安部公房自身は、東大医学部出身からわかるように、いわゆるエリートであるが、彼の作品の登場人物は、社会から疎外された者がほとんどである。「箱男」や「方舟さくら丸」などは、極端な例だが、他にも、職業に生き甲斐をもてず、妻とも不仲になっているような、孤独な男が、主人公になることが多い。「砂の女」や「燃えつきた地図」などがそれに当てはまるだろう。